蓮の花はお好きですか?
そろそろ暑くなろうかという頃、水辺に咲くピンクや白の清楚な花は、なんとも清らかな気持ちにさせてくれますね。
毎年6月も後半になると、あちらこちらから蓮の花の便りが届きます。
蓮は早朝6時頃から開花し、ピークは9時頃で、正午には閉じてしまいます。
そのため見に行く時間はぜひ午前中に。
翌朝にまた開く訳ですが、3日目頃からはしっかり閉じなくなり、4日目にはそのまま散るのだそうですよ。
一輪一輪は短い花期なんですね。
そして場所や品種によって、咲く時期が異なります。
せっかく見に行くのなら、ちゃんと咲いていて欲しいですよね。
とうわけで身近で見られる蓮の時期を調べてみました。
国営木曽三川公園の近く
今回訪れたのは木曽川と長良川が合流する、岐阜県と愛知県の境目あたりの木曽三川地域です。
このあたりは土壌がレンコン栽培に適しており、昔からレンコンの生産が盛んです。
なので、さぞや時季になると美しい蓮の花がたくさん見られるのでは?
そんな期待を持って有名な所を辿ってみたら、地図上でほぼまっすぐなので、何か所か一度に廻ることも可能だとわかりました。
筆者は三重県や滋賀県によく行くのですが、なんとその通り道と言っても良いルート上でした。
これは好都合!
大賀ハス園
大賀ハスは1951年、千葉市の縄文~弥生時代の遺跡から出土した3粒の古代ハスの実を植物学者の大賀一郎博士が育成、開花させたことから名づけられました。
その後千葉公園の池などで増殖されていましたが、羽島市はレンコンの伝統的生産地であることから、1979年に市制施行25周年記念として株分けをしてもらったということです。
園では大賀ハスと舞妃蓮が植えられており、その違いも楽しめます。
場 所:岐阜県羽島市桑原町前野 県道134号線沿い
駐車場:3台ほど
隣の羽島温泉の駐車場を利用すると良いです
見 頃:6月中旬~7月上旬と言われています
6月30日 大賀ハスは咲いておらず舞妃蓮が見頃
車を羽島温泉駐車場に置かせてもらい、少し北に歩いたところから見た風景です。
細い用水路を挟んだすぐ横から大賀ハス園が始まります。
案内板のすぐ後ろが大賀ハスですが、花がありません。
え、え? これから咲くんでしょうか、それとももう終わった?
元々育てるのが簡単ではなく、花も少なめなんだそうです。
そうですよねぇ、なんたって古代ハスですから。
本家本元の千葉公園では6月の初め頃から花がつき始め、6月中旬~7月上旬がピークのようなのです。
なので、ちょうど良い頃と思ったのですが…。
今日は残念でしたが、まぁ、また来てみることにしましょう。
大賀ハスの奥に白い筋のように見えているのが、舞妃蓮という品種で、こちらはちょうど見頃でした。

駐車場のある農道側から見た風景です。
白い建物が羽島温泉、その前のライトグリーンのフェンス一帯が駐車場です。
舞妃蓮が満開です。

咲き始めのものはふっくらした印象ですが、日が経つと花弁が伸びる感じですね。
舞妃蓮の特徴で、開花2日目以降はひねりが入り、高貴な女性が舞うような優雅さがあることから「舞妃蓮」と名付けられたそうです。
別の品種のように見えてしまいそうですよね。


7月9日 大賀ハスが開花していました
右が大賀ハス、左は舞妃蓮です。丈がずいぶん違いますね。
舞妃蓮は変わらず見頃。
大賀ハスはこの日もあまり花が見られませんでしたが、数輪美しく咲いていて感激!

数少ない、咲いている大賀ハスです。
つぼみもあるので、これからが咲く時季なんでしょうか?

大賀ハスの特徴は
・花弁の条線(濃いピンクの筋)がほとんどない
・葉はざらつかず滑らか
だそうです。
こんなに滑らかな花弁のハスは初めて見ました。
大賀ハスって、こんなに神秘的な美しさなんですね。
来年は是非たくさん咲いて欲しいものです。

舞妃蓮はこのとおり花盛りです。
つぼみも多いので、まだまだ咲きそう。

園の北東の一画に、ちょっと咲き方の異なるものがありました。
隣の区域の白っぽい舞妃蓮よりややピンクが濃い感じで、数日前らしい花も舞っているような、いないような?

取り立てて別の札もないので、これも舞妃蓮なのかな?

8月1日 すでに花期終了
7月中にもう一度来ればよかったのですが、8月に入ってしまい、完全に花期が終了していました。
舞妃蓮はすでに葉も枯れ、茶色の花托が目立つ所や、株もなくなって水が張ってあるのみの所も。
そして大賀ハスの方は、前回の訪問後に咲いて散ったんでしょう、まだ緑色の花托がそこここに見られます。
もうつぼみもないので、こちらも終了。
大賀ハス園の見頃は6月中旬~7月中旬頃までですね。
そのうち大賀ハスに限っては7月上旬~中旬頃の短い期間でした。

立田赤蓮保存田
赤蓮は江戸時代の文政~天保年間に、当地の陽南寺の住職で漢方医でもあった竜天和尚が、近江国から持ち帰ったとも、肥後国から来た僧から譲り受けたとも言われています。
最初は観賞用でしたが、その後に地下茎が食用になるとわかり、当地の特産品として各地に広がったとの事。
天然記念物になっている「立田赤蓮」の立田はここがかつて立田村と呼ばれていたからです。
花弁は18枚前後で先がとがり、内側の花弁は数枚が内側に曲がっており、花色は濃紅で条線が鮮明なのが特徴だそうです。
かつては日本各地に分布したという赤蓮ですが、今ではこちらを含め数か所にしか残っていない、貴重な蓮です。
場 所:愛知県愛西市小茂井町保古原
駐車場:なし
愛西市役所立田支所の駐車場を利用を推奨
見 頃:7月上旬~8月上旬と言われます
6月30日 まだ早過ぎました
7月上旬からなら、6月末でも良いかと思ったのですが、ちょっと早かったです。
丈もそんなに高くないし、まだほとんど花も見えません。

保存田らしく、番号と品種を記した木札が立っていました。
一画には大賀ハスの名も。
中に入って行けるようなデッキも作られていたので、上って見ると、隠れて小さなつぼみがほころんでいました。

おお、さすがに濃い赤のつぼみと思ったら、あれ?「白加賀」なんですか?

ここに至るまでの道中、道の右も左もその奥も、いたる所に蓮田がありました。
そう、愛西市はレンコンの名産地なのです。
そのため、観賞用ではなくても蓮の花が咲き乱れるはず、時季が来れば。
そんな期待もあって、ぜひ訪れて見たかったのです。
ただ、花を観賞する花はすと異なり、レンコンを収穫する用の蓮は、花も少し違うのかもしれませんね。
下の写真は保存田の周辺にある、一般の蓮田?の様子です。
こちらも花はまだまだこれからのようです。

7月9日 花が増えてきました ピーク間近
さて、7月の上旬になりましたよ。
ということで再訪しました。
丈が伸びており、デッキも覆い尽くされそう。

上って見ると、葉っぱの上には出ていなくても、隠れて咲いているものや、もうすぐ咲きそうなつぼみがたくさんありました。

品種によってはもう少し背丈が低く、花も葉っぱの上に出ていました。
名前に「紅蓮」がついてますけど、どう見ても赤蓮じゃないですよね。
6月の写真にも赤い「白加賀」が写ってましたが。
混植なので隣近所から遊びに来るんでしょうね。なにしろ地下茎だから。
でもきれいです。

まるでシャクヤクのような、ハス。

これが「赤蓮」なのかな。
立田赤蓮は赤が強いのが特徴なんだそうです。
個人的にはもっと赤いかと、勝手に想像していましたが、どうなんでしょう。
この日見た花のうちでは一番赤いです、

周辺の蓮田にもそろそろ花が増えてきましたね。

こちらは少し離れた周辺の蓮田ですが、ずうっと向こうまで蓮田が続いているのがわかるでしょうか。
これだけ広い蓮田があちこちに見られるのは圧巻です。
この蓮田はピークと言って良いかも。

8月1日 今まさに見頃
羽島市の蓮園では、すでに見頃が終了していましたが、愛西市では今まさに見頃と言ったところです。
丈も伸びデッキはすでに覆い尽くされていて、ここをかき分けて進む気にはなれませんでした。

外からでも花数が増えたのがわかりますし。

群馬紅蓮もちゃんと赤い花が咲いていました。

7月上旬に見られなかった大賀ハスも、今日は丈高く咲いています。

周辺の蓮田もまだまだ見頃です。
赤蓮保存田とその周辺の蓮田の見頃は、7月中旬から8月中旬頃かもしれませんね。

8月19日 保存田はすでに終了 周辺もピークは過ぎた様子
前回8月中旬までと予想した訳ですが、中旬を過ぎた本日は、緑色の花托ばかり。
花が散ってから少し時間が経っている様子です。
状態の良い花を見ようと思うと上旬のうち、つまり10日頃までに、と思った方が良いのでは。
他に本日気がついたのは、細かいことですが「藤壺蓮」という品種は、この時期にやっとこの丈なのだということ。
6月30日にまだほとんど水面しか見えていなかった区域で、8月1日には低い位置で花を付けていた品種です。
というよりは、他の蓮が丈高過ぎなのかも?
わかりませんが。

名残りの数輪のうちのひとつ。
品種はわかりませんが、最後まできれいです。


周辺の蓮田も少しずつ花数が減っています。
それでも、ややピークを過ぎたかなくらいにしか見えないのは、実は驚異的なのかも。
まだつぼみも見えますもんね。
別の蓮田ではすでに枯れた水上が撤去され、水だけが張られていたところもありましたから。
ということで、立田赤蓮保存田の見頃は7月中旬から8月10日頃、周辺の蓮田は8月下旬頃とさせていただきます。
このあたりはいたる所に蓮田がありますが、その全部でこんな感じに花盛りになる訳ではありませんでした。
6月末から8月後半まで、一度も花を見なかった蓮田が多いのです。
確かに、レンコンの収穫が目的なら、必ずしも花を咲かせる必要はありませんもんね。

森川花はす田
場 所:愛知県愛西市森川町村仲
見 頃:7月上旬~8月上旬と言われています
都市公園化に向けての工事中で、2026年2月27日まで立入禁止になっています。残念!
船頭平(せんどうひら)河川公園
船頭平河川公園は国営木曽三川公園のひとつで、広い駐車場から直接水生植物園に行ける道と、デレーケ像や庭園、閘門を通って行く道とがあります。
この河川公園には船頭平閘門という、門の開閉で水の高さを調整し木曽川と長良川の間を行き来するための門があるのです。(国指定重要文化財)
蓮が目的なら前者でOK。広い駐車場があるのはこちらです。
ただし開門は9:30から。
場 所:愛知県愛西市立田町福原
駐車場:68台(無料)
見 頃:6月中旬~7月上旬とも、7月~8月とも言われます
休園日:基本的に月曜日
公式HPで確認をおすすめします
6月30日 遠目ですが咲き始め
直接蓮池に向かうつもりでしたが、まさかの休園日。
調べてきたつもりだったのに、ケアレスミス。
ゲートががっちり閉まっていて、遠目にしか見えません。
低い木の足元に蓮らしき茂みが見えます。
ポツポツとは咲いている様子。
でもなんだか蓮池の範囲が小さくないでしょうか?一抹の不安がよぎります。

7月9日 見頃でした
せっかく重要文化財があるならと好奇心が沸いて、今日は正面から行くことにしました。
庭園を抜け、デレーケ像に敬意を表して、閘門を横切りました。
これが船頭平閘門の上流側です。
見えている門の向こうは木曽川、貯水池を挟んで後方が長良川ですが、もちろんここ自体は本流ではなく、本流から本流にスライドするつなぎ目のようなものかな。
木曽川と長良川の川面の高さが異なるので、ここで調整して移行します。
パナマ運河がこれ式ですが、日本ではここが初だそうです。


閘門を抜けると水生植物園に出られます。
ただ蓮池の規模が、拍子抜けするほど小さいです。
ここに来る前に広大な蓮田を見てきてしまっているから、余計そう見えてしまうのかもしれませんが。
近所の公園の花壇くらいかなぁ。
4年ほど前のスタッフブログ等見ていると、もっともっと広い範囲に繁っている様子だったんですけれどね。
それでも、品種はわかりませんが、きれいな蓮が咲いていました。
船頭平河川公園の蓮の見頃は7月上旬~下頃頃ということで。


8月19日 蓮は終了 閘門の開閉時に遭遇
蓮は前回の訪問時がピークの様子だったので、もっても下旬だろうと結論づけました。
本日確認のため立ち寄ってみたところ、葉だけが残っていました。
ただ、偶然ですが、閘門の開閉に遭遇したんですよ。
点検のため毎朝一度開閉するのだそうです。
おおーと思い上からは撮影したものの、すぐに閉門が始まったので、慌てて正面に走りやっと撮影したところです。
明治35年に完成した国の重要文化財で、今も現役なんですって! すごいな。
これは下流側の門で、門の向こうは長良川。
正面の庭園から蓮のある側に抜ける道は、この門の上に通っています。

2025年 木曽三川地区の蓮の見頃 まとめ
木曽三川地区は木曽川・長良川・揖斐川の集まる所で、昔から川の氾濫などで川筋が何度も変わる等の水害にたびたび見舞われてきた地区です。
薩摩義士やデレーケによる治水のおかげで、今は花を愛でられるような平和な土地になりました。
洪水が作ってきた土壌が蓮に適したことと、産業にできたことは、これぞ仏様のご加護かも。
蓮に限らず、花の見頃というのはその年の気候にもよるので、例年の見頃とはズレたりします。
筆者が今年実際に見てきた様子から、独断による見頃をご報告しますね。
木曽三川地区の蓮の見頃は
大賀ハス園 6月中旬から7月中旬 そのうち大賀ハスは7月上旬から7月中旬
立田赤蓮保存田 7月中旬から8月10日頃まで
周辺蓮田は7月中旬から8月下旬頃まで
(一般の蓮田全部に花が咲く訳ではない)
森川花はす田 6月下旬から8月上旬と言われています
都市公園化工事中のため、2026年2月27日まで閉鎖
船頭平河川公園 7月上旬から下旬頃
来年にこの通りの見頃とは限りませんが、一つの記録とします。
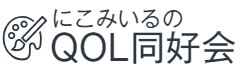



コメント